小学校3年生になると、算数の学習で「長い長さ」の単元に取り組みます。その中でも特に子どもたちが興味をもつ活動のひとつが、「巻き尺を使った実測」です。今回は、巻き尺を使わずにフラフープの周りの長さを測ってみるという、ちょっと変わった授業を通して、子どもたちが「巻き尺のすごさ」を実感する様子をご紹介します。

算数では「物」に触れながら学習を進めることも大切ですね!
えっ、巻き尺を使わないでフラフープを測るの?
導入では無言でドンとフラフープを子どもたちに見せました。
すると、子どもたちは「え!?」「なにすんの!?」とざわざわします。
そして、このように子どもたちに問いかけしました。
「このフラフープのまわりの長さ、どうやって測ればいいと思う?」
子どもたちは、驚いたような顔をして一斉に考え始めます。
「ひもを巻いてから伸ばして測る!」
「ジャンプして何歩分か数える!」
「物差しを少しずつ動かして測る!」
さまざまなアイディアが飛び出したところで、1度実際に測ってみることにします。
今回は一人ではなくグループで進めることにしました。
試行錯誤こそが学びのタネ
「測る」という活動は、ただ結果を出すだけではありません。
この活動の大きなねらいの一つが、子どもたちが試行錯誤しながら方法を工夫しようとする姿勢を育てることにあります。うまくいかないことを何度も繰り返す中で、「どうすればもっと正確に、もっと楽に測れるんだろう?」と考える力が自然と身につきます。
また、子どもたちが自分のアイディアで挑戦することで、学びが「自分ごと」になっていくのです。

授業の主導権を子どもに渡す。授業の先頭を子どもが走る。
そのようなイメージで進めていきましょう。
そして登場!巻き尺の登場に子どもたちが驚いた理由
こうしてあれこれ試したあとで、巻き尺を取り出して実際に測ってみます。すると、あっという間に正確な長さがわかるのです。
「うわ、めっちゃ簡単やん!」
「最初からこれ使えばよかった!」
子どもたちの目がキラリと光ります。ここでようやく、「巻き尺ってすごい道具なんだ!」という実感が生まれるのです。
この「遠回りのような学び」こそが、道具の有効性を深く理解するための近道になります。

巻き尺の使い方はしっかりと教えましょう。
「教えるところは教える」です。
日常の“なんで?”を大切にする授業づくり
今回の授業のように、わざと遠回りをさせたり、不便さを体験させたりすることは、一見すると効率が悪いようにも見えます。
しかし、この「不便さ」こそが、「便利さ」を感じるための出発点になります。子どもたちは、自分で苦労してみることで、道具の価値を実感するのです。
巻き尺で広がる子どもたちの世界
次の時間では巻き尺を手に校内を歩き回り、いろいろなものを測り始めました。黒板、下駄箱、ベンチ、教室の床、木の幹…。
「え、これってこんな長さあったんや!」
「これって同じぐらいの長さかな?」
そんな声があちこちから聞こえてきます。巻き尺という新しい道具に出会ったことで、子どもたちの目に映る世界が一気に広がった瞬間でした。

ここでワンポイント!
ただ測るのではなく「これは○mぐらい」と予想させてから測りましょう。
最後に
このように、学習の中で「試行錯誤」や「道具の活用」を体験することは、これからの時代に求められる「主体的に学ぶ力」を育てる土台となります。
巻き尺との出会いを通して、子どもたちは長さを測る方法以上に、学ぶ楽しさや工夫する喜びを感じることができました。
先生が答えを教えて終わり、という授業ではなく、 子どもたちが「あーでもない、こーでもない」と考え、悩み、試すこと。その過程こそが、算数の本当の楽しさであり、学びの魅力なのだと思います。


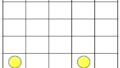

コメント